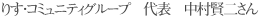



滋賀県の農家に生まれた。父はさしもの職人や大豆の行商のかたわら手堅く農地を買い広げ、母と共に早朝から農作業に精を出して家族を養う姿を見て「農家だけにはなりたくない」と思った。農繁期にはテストよりも家の手伝いが優先で「勉強しろ」とは一度も言われず、母に代わって毎日の弁当も自分で作り、自立心が養われた。
学校では何事にも模範的な兄といつも比べられた。ただ母は「自分の好きなようにやればええ」と言ってくれて、放課後は仲間を引き連れて野山を駆け回った。近所の家の柿を盗って、何度もゲンコツをもらっても、「悪いことは悪い」と教えて、えこひいきしない先生が好きだった。
中学になると実力テストでは220人中30位程度で「進学校へ行け」と両親に言われることもない。住職のかたわら音楽を教え「自由な道で生きろ」と言う担任に憧れてたびたび家に遊びに行きつつ、「高校生になったら自分でお金を稼いで自由に遊びたい」と考えていた。苦労人の父は将来国鉄への入社が固い鉄道学校への進学を勧めたが、多くのOBがビジネスで成功を収める名門八幡商業高校を自ら選んだ。
ただ、厳しい練習で休日もないバスケ部は半年で辞めて、流行のグループサウンズのバンドを組んだがそれにも夢中にはなれない。「学生帽をかぶれ。詰襟のホックを留めろ」と規則ばかり押し付ける先生に反抗し、授業が休講になるとそのままボウリング場に直行して、興味の持てない教科に1がついても特に気にならなかった。
3年生になると大手商社や繊維関連の会社から次々と高校に求人が舞い込み、内申点の高い級友は就職を決めて行く一方で、「自分は家を出て自立したい」と考えながら進路指導部の推薦を必要としない日本専売公社の入社試験を受けた。

ニースでの一枚。ビジネス学校の後、3ヵ月をかけて欧州を回り自由を満喫。自立への思いは強まった。
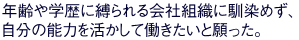
19歳から25歳までの6年間は迷いの連続だった。気の合う同僚にも恵まれ、福利厚生もしっかりして安定はあるものの、独占事業で他社との競合もなく、年功序列や学歴で出世が決まる公社。週末のたびに洗濯物を抱えて実家に帰り、上司への中元に親から高級ブランデーを送ってもらう同僚たちを見て、自分の育ってきた環境との違いを感じた。更に、試験をパスし、年を重ねれば一定のポストが約束される社内制度に、「これは自分の進む道じゃないな」と思い、将来の選択肢を広げようと仕事のかたわら、大学受験勉強に取り組んだ。
21歳で入学した大学では必要最小限の単位を取り、学費と生活費を稼ぐアルバイトに明け暮れた。しかし、英語の必要性を感じて「一度は国外に出たい」とイギリスに渡り、懸命に学ぶ他の留学生たちに刺激を受けながら英語の資格FCE(First Certificate in English)を手にした。更に「実社会で役立つ勉強がしたい」とビジネス学校にも通う。「技術を持って、会社に縛られることなく働きたい」と強く感じた。
帰国後に「英語という技術を活かそう」と始めた予備校や塾講師と家庭教師のアルバイト。小中高と勉強に興味が持てなかった自分の経験から勉強嫌いの子どもの気持ちを理解できて、「これは自分に向いているのでは」と思うようになった。
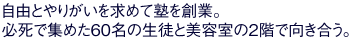
26歳になって、「もっと本格的にビジネスを学びたい」と考え、アメリカの大学院留学の願書を取り寄せ、入学に必要なTOEFLの点数もクリアした。「そのためにはとにかく金が必要や」と知人のツテで安く借りた風呂なしの古い長屋に住んで、昼間はトラックで建材を運搬し、夜は塾講師とひたすら働いた。更に家庭教師もかけもち、有名大学を目指す子どもから勉強嫌いの子どもまで教えて、ふすま越しに聞き耳を立てる親の思いをひしひしと感じる。塾では生徒や保護者から圧倒的な支持を受けて塾長から運営を任される程の信頼を得た。また、他の塾から講師の誘いを受けて自信をつけた。
28歳になって、がむしゃらに働いて貯めたお金は既に800万円に達していた。しかし、目指すアメリカ留学の先に何か夢があるわけではないと思い悩んだ。ただ企業勤めをする気にはなれなくて「このままフラフラしていても将来は見えない」と、今の技術を活かして自分で塾を開くことを決心した。
美容室の2階を間借りして生徒集めのチラシをまいた。しかし、自らの指導力への絶対的な自信とは裏腹に一軒一軒訪ねても玄関すら開けてもらえず、悔しさを噛みしめる。市役所で閲覧した住民票を元に片っ端から電話をかけて、母親を前に「合格せんかったらお金は返します!」と言い切った。ようやく集まった60名の生徒を前に「俺を信じて子どもを預けてくれたんや」と母親たちの顔が浮かぶ。講師の給料を払うために家庭教師もしながら懸命に塾を運営すると着実に有名校への合格者も出て、翌年に2校目を開校できた。
決してえこひいきをせず、隣のクラスにも乗り込んで大騒ぎする生徒を怒鳴りつけ、何度も手を上げた。受験に失敗した生徒全員に励ましの手紙を書き、一人ひとりの個性に合わせた指導で着実に生徒数は増え続けた。