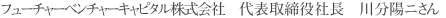
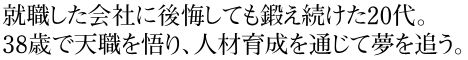

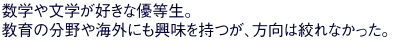
彦根市で生まれ、幼稚園のときから人から指図されるのが大嫌いでいつも外を駆け回って遊ぶガキ大将。学校の先生が教えてくれる大陸移動説やアメリカンフットボール、父が戦時中に派兵されたスマトラの話など、新しく見聞きすることに強い興味を示した。
NTT技師の父の影響でラジオなどの通信機いじりが好きで、科学者を夢見て理数系を中心に成績は群を抜いていた。母が苦しい家計を支えて農作業や内職をする傍らで、料理教室で栄養指導をしたり、琵琶湖の汚染問題に懸命に取り組む姿を見て育った。
中学になると少し色弱なことがわかって、医者や科学者になることを断念。文学書の乱読や放送部での番組づくりを楽しむ一方で、バスケ部のレギュラーとして活躍、生徒会長も務めてみる。母の期待に応えて勉強もし、京都の国立大付属高に受かる学力もあったが通学時間が無駄に思えて、私立受験もせずに県下有数の公立進学校に進んだ。
しかし、質実剛健で自由な校風とは裏腹に、まじめに勉強することをあまり認めない級友たちの雰囲気に違和感があった。アメフト部で体力をつけながらも読書時間が増え、おさな児を題材に短歌を作って投稿すると入賞もする。与謝蕪村の生涯を調べて授業で発表すると、みんなが目を輝かせて聞いてくれていて、教員の仕事にも興味を持った。
少しでも難関な進路に挑戦しようと、法律に興味もないのに一浪をして京大法学部へ。学生を大人として認めてくれる有名教授に魅かれて、国際政治学のゼミに進んだ。全国から集まる秀才たちに刺激を受けながら、友人と塾を開くなどして資金を貯めては日本全国や海外を旅して、日本のインドネシア占領政策を研究した。ただ、大学院進学や文部省を目指すことも考えたが、将来の方向を絞り切れないままに4回生の秋になった。

アブダビ国立銀行勤務時代に家族でロンドン旅行。まだ、経営者になることなど考えてもいなかった。

そんな中でOBに誘われるままに受けた住友銀行から内定が出て、「経営者を育てる銀行や」という言葉に魅かれて入行。しかし、「男は24時間仕事だ」と体育会のノリが主流で、休日でも寮のイベントを欠席しにくいなどの当時の集団主義に面食らった。そして、都心の支店に配属され、担保を持たない経営者の相談にはほとんど乗ろうとせず、顧客のことより店の利益を優先して会話する現場を目の当たりにして、すぐに「ここは違う…」と辞めたくなった。営業成果が上がらなければ一人前にも扱ってもらえず、完全に自信を失い、思い余って受けたテレビ局の採用試験でも不合格になって一人落ち込んだ。
もう我慢できない、と思うたびに転勤になり、「このままでは悔しい。とにかく結果を出そう!」と、中小企業の経営者を追いかけ、夜討ち朝駆けで夢中に営業する日々。想像もしない道を歩む自分を感じながらも、いつしか5年が過ぎていた。28歳で結婚をしたときに、「転職は35歳まで、50歳に学者になる」と、「人生20年計画」を書き記した。
大手企業を担当する支店に勤務していた32歳の頃、「海外に行きたい」と言い続けてきた念願がかなって、同期の中から4〜5人しか選ばれない語学研修生に抜擢。その後、アラブ首長国連邦の国立銀行へたった一人で派遣され、欧米人の上司たちと渡り合って自分に自信を蘇らせた。そこのバンカーたちが、土地などの担保がなくても、事業の将来性に対して当たり前のように融資をする姿が新鮮に思えた。しかし、2年後の1988年に帰国して配属されたのは、東京駅前支店の不動産担保ローンの与信管理だった。
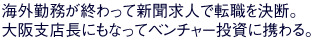
海外経験もまったく活かせず、バブルに浮かれ、「値下がることはない土地」を担保に、顧客に頼まれもしない融資を押し付けて利益を上げる銀行に失望し、「もうここには居場所はない…」と思っていた半年後、一つの新聞求人が目に入った。アジアで事業展開する日本企業に投資をする半官半民の会社。「これこそ私がやりたい仕事だ!」と、財閥系銀行に勤務する名を捨てて転職した。自分で転職のリミットとしていた35歳だった。
将来を見込んだ会社に投資して、アジアでの戦略などを助言していく業務。命を賭けて事業に臨む経営者と同じ視点で仕事をするために必死に勉強し、日に日に自分の能力が高まっていく実感がした。自分が見込んだ会社に1億円の追加出資をすると、経営が軌道に乗って上場を果たしたりする醍醐味を味わった3年後、大阪支店長を任された。
海外との接点はなくなり、国内ベンチャーへの投資に業務が変わるが、リスクを背負った経営者と二人三脚で先々を予測して戦略を打っていくこの仕事が天職のように思えた。ただ、20代10数人の育成も任されてリーダーシップを求められ、「部下に信頼されるためには正論や合理性だけでなく、一緒に泥をかぶる覚悟が必要だ。それが僕にできるだろうか…」と、不安になった。「とにかく逃げることだけはしてはいけない」と肝に銘じて、本社や顧客と自ら妥協なくぶつかった。朝一番に出社して、深夜まで猛烈に働いて範を示すと、次第に部下たちは意欲高く業務に取り組み、目を見張るように成長してくれた。
しかし、ベンチャー企業を見る自分の目に自信を深めても、東京本社からの投資許可は思ったように下りない。「なぜ、私の判断を認めないんだ…」と不満は溜まっていった。